
「病気に強い犬種」としても有名な柴犬。日本の気候にも慣れているためか、暑い夏や寒い冬を余裕な表情で乗り越える姿はとても頼もしいですよね。
しかしそんな柴犬でも、もちろん全く病気にならないということはありません!
柴犬がかかりやすいと言われている病気がいくつかあるので、この機会にぜひ知っておいていただけたらと思います。

皮膚の病気

アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、柴犬がかかりやすい代表的な皮膚の病気です。柴犬の場合、遺伝的な要因も大きいと考えられています。
花粉・ハウスダスト・ダニなどの吸引や、食事やおやつなどの摂取により、何らかのアレルゲンを体に取り入れることで引き起こされます。
症状
アトピー性皮膚炎になった柴犬は、体や顔を掻いたり、肘や内股、足の裏を舐めたります。ひどい場合は皮膚がただれて血が出てしまうこともあるので注意しましょう。
とくに耳・目・お腹周り、四股の付け根などに症状が出やすいと言われています。
また中には、毛が抜ける(脱毛)犬もいるようです。皮膚だけでなく被毛にまで影響が出るので気をつけなければなりません。
予防&対策方法
アトピー性皮膚炎の予防法としては、普段から体を清潔に保つことが大切です!柴犬のシャンプーは大変ですが、できるだけ月に1回のペースでシャンプーできるよう、がんばっていきましょう。
食物アレルギーが考えられる場合は、食材の種類を制限をすることが、食事からアレルゲンを摂取する可能性を減らします。
ただ、いくらシャンプーやフードに気を配っていても、痒みがコントロールできない場合はあります。その際は動物病院を受診し、痒み止めの薬をもらうようにしてください。
脳の病気

認知症(正式名称:認知機能不全症候群)
柴犬は比較的病気になりにくい犬種ですが、老犬になると認知症を発症することが多い犬種で知られています。
実は柴犬含めた日本犬の多くは、「体が丈夫で寿命が長い」のが特徴です。
洋犬は心臓や腎臓、胃腸などの内臓が脳より先に悪くなることが多く、死に至ります。柴犬は体が強いからこそ内臓よりも先に脳が悪くなり、認知症が目立ってしまうと考えています。
症状
認知症の症状は実に様々です。例えば以下のような行動や傾向が見られます。
- 同じところをグルグル回ったり、うろついたりする。
- 物にはさまって動けなくなる。
- 飼い主や知っているはずの人間や犬、場所がわからなくなる。
- 呼ばれてもすぐに反応を返さない。
- 家族や知人とのふれあいに喜びを示さない。
- 家族や訪問者、犬に対してイライラや恐怖を示す。
- 夜間になっても眠らない(昼夜逆転の生活)。
- 夜間に鳴いたり吠え続けたりする(夜鳴き)。
- トイレではない場所で粗相をする。
- 新しいことを覚えられない。
- 学習済みのはずのコマンドができなくなる。
該当する項目が多い場合には認知症の可能性がありますので、動物病院へ相談するようにしてください。
予防&対策方法
認知症の予防として効果的なのは、散歩コースを頻繁に変えてみたり、頭を使った運動や遊びをしたりすることです。常日頃から頭を使うことで、脳に刺激を与えることができます。
認知症は老化の結果ともいえるため、根本的な解決は望めません。飼い主さんと飼い犬がうまく付き合っていける道を探していきましょう。
一般的によく使われているのはサプリメントです。最近では認知症にも有効とされているドックフードが販売されています。
最も飼い主さんが困る症状が夜鳴きです。近所への騒音問題や飼い主さん自身の睡眠不足にも悩まされます。
そういった場合はかかりつけの動物病院で睡眠薬を処方してもらうとよいでしょう。睡眠薬を使用する場合、適切な強さや量は個体差が大きいため、獣医さんとよく相談するようにしてください。
目の病気

白内障
目の中にある水晶体が、白く濁って視力が低下していく病気です。老化が主な原因ですが、遺伝や糖尿病などが原因の場合もあります。
症状
視力が低下してくると、暗い時の散歩を嫌がる、側溝にはまる、階段を踏み外すなどの症状が認められます。
家の中で物にぶつかるようになると、ほとんど見えていない状態です。
予防&対策方法
白内障は老化あるいは遺伝が原因であり、対策方法はありません。進行を遅らせる目薬や、水晶体を保護するサプリメントがありますので、動物病院で相談してみてください。
結膜炎
結膜炎とは、白目の表面とまぶたの裏側をおおう結膜に炎症が起きた状態です。結膜炎の原因は、角膜のケガ、涙量の不足、アレルギーなどです。
体の痒みが原因で、後ろ足で掻いたり、タオルなどに顔をこすりつけることで角膜を傷つけた場合には大きな問題となることがあります。
繰り返し強く掻くことで、角膜に大きな傷ができることがあります。
症状
結膜炎になると、白目の充血、粘膜の腫れ、涙量の増加、黄色い眼脂などが認められます。
予防&対策方法
動物病院を受診し、適切な点眼薬の処方を受けてください。また、同時に痒みのコントロールも必要です。エリザベスカラーの着用や痒み止めの使用を検討しましょう。
家庭では愛犬の目の周りを観察し、清潔に保ってあげるようにしてください。
耳の病気

外耳炎
外耳炎とは、耳の入り口から鼓膜までの外耳道に炎症が起きた状態です。
原因は様々ですが、アレルギー体質・耳毛の量・耳の形状(垂れ耳)等が考えられます。炎症のある耳道は、抵抗力が低下し、細菌や真菌が繁殖し、臭いや耳垢が増加します。
症状
後ろ足で耳を掻く、頭を振るのは痒みの症状です。耳が赤くなり、腫れます。耳垢が増加し、臭いが強くなります。
予防&対策方法
指で届く範囲(入口だけでもOK)の汚れは定期的に取り除くようにしましょう。
赤みがある場合やにおいが強い場合は外用薬が必要です。液体を耳に垂らす点耳薬や、クリーム状の薬を塗る軟膏などがあります。
また、新しい薬として、1回薬を入れると、1か月間効果が続く薬もあります。家で耳掃除ができないワンちゃんは検討してもいいかもしれません。
行動学的な病気

問題行動
日本犬の一種である柴犬は飼いやすいというイメージがあるかもしれませんが、実は問題行動の発生が目立つ犬種です。
柴犬は番犬をする目的で改良されてきたという歴史があります。侵入者に対して吠える能力のある犬、体が大きな犬が優れたものとして繁殖されてきました。
柴犬はどちらかというと人への愛着や依存度が低い反面、獲物追跡傾向や攻撃性が高いという調査結果もあります。
特に近年は屋外よりも室内で犬を飼う傾向にあり、家族と同じスペースでともに過ごす時間が増えたこともトラブルが起こる一因となっているようです。
症状
柴犬の問題行動には以下のようなものがあります。
- 家族に対して唸ったり噛みついたりする(攻撃行動)。
- 自分の尾を追いかけたり噛みちぎったりする(常同行動・自傷行動)。
個体差もあるものの、スキンシップや拘束を苦手とする柴犬は多く、攻撃行動は飼い主さんのちょっとした行為がきっかけになることも珍しくありません。
例えば、首輪を手に持ってリードをつけたり、抱っこをしようとしたりすることもきっかけの1つ。ごはんやおやつを食べている時に近付いただけで攻撃性を示す犬もいます。
単になでることやブラッシング・シャンプーを嫌がる柴犬もいるため、トレーニングや世話に苦労する飼い主さんもたくさん見られます。
予防&対策方法
問題行動の予防として考えられるのは、まず誤ったしつけを行わないこと。
飼い主さんの威圧的な態度や仕草、体罰などは柴犬の攻撃性を高める恐れがあるだけでなく、お互い良い関係性を作るためにもおすすめできません。
子犬であれば、適切な時期に社会化トレーニングを行うことも大切です。
新しい状況を受け入れるのが苦手な柴犬だからこそ、早い段階で人が暮らす環境や物音に慣れてもらうようにしましょう。
方法に迷ったときは、しつけ教室も検討してみてください。
室内で飼うのであれば、クレートなどで柴犬専用のスペースを設けるのも対策方法の1つです。
ただ、柴犬の問題行動は、ケガやほかの病気が隠れているケース、脳疾患やホルモンの異常が関係しているケースもあります。
行動療法や薬物療法など、それぞれ対策や治療方法は違ってくるため、そういった意味でも早めに動物病院で診察してもらうことをおすすめします。
もし今後柴犬を飼うことを考えているのなら、家族に小さな子どもがいる場合は特に、家庭で適切なしつけができるかどうか事前によく検討することが大事です。
柴犬は体が丈夫で、大きな病気にかかかりにくい犬種です。だからと言って油断していると、誰が見ても分かるような病気にさえ気づいてあげられないこともあるので注意しましょう。
「柴犬だから大丈夫!」「柴犬だからこの病気にはならない!」と勝手に決めつけず、必ず定期的に健康診断を受けて早期発見・早期治療に努めるようにすることが大切です。
飼い主さんができることは、わんちゃんの健康管理を毎日行うこと。そして食事・運動・お手入れ・空調など、とにかくわんちゃんが快適に過ごせる環境をつくってあげましょう。

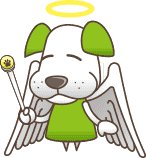



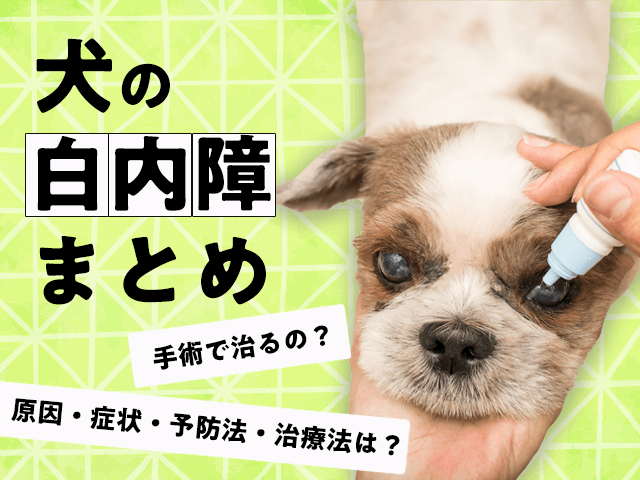
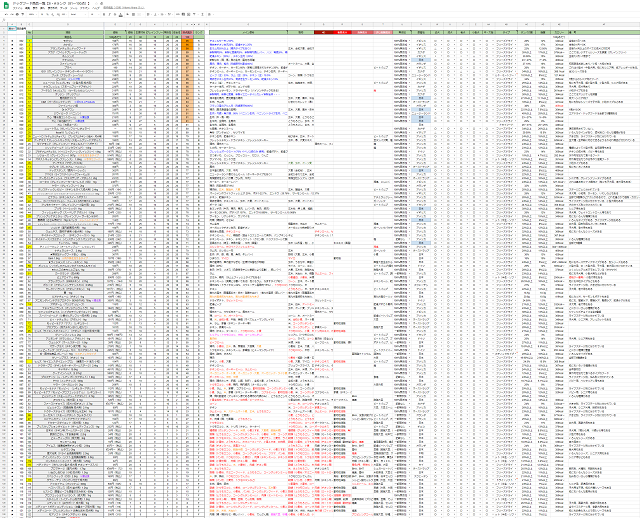

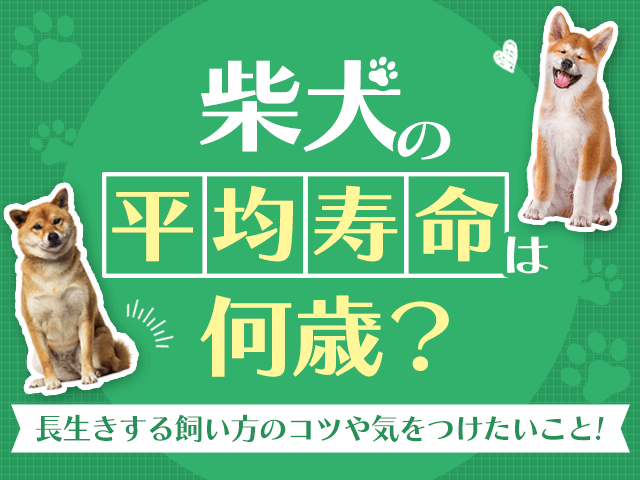






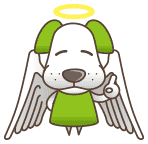

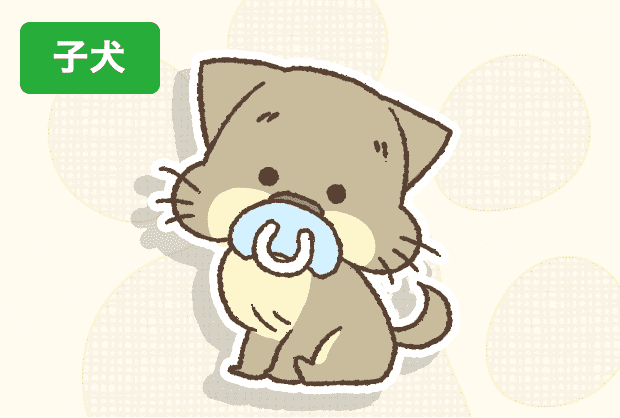
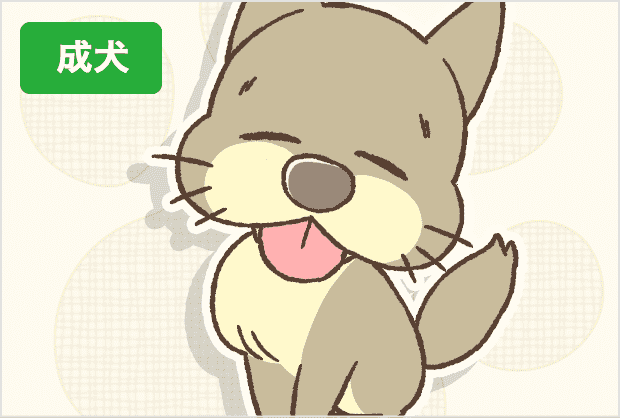
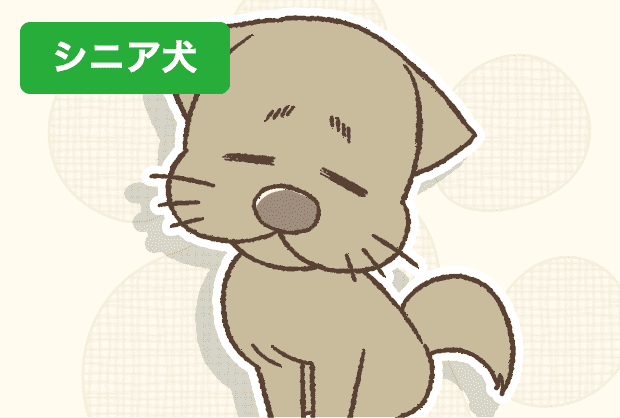


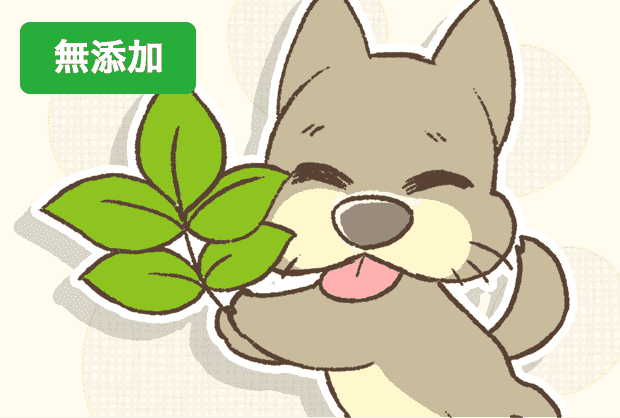


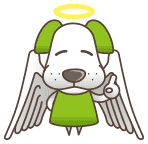







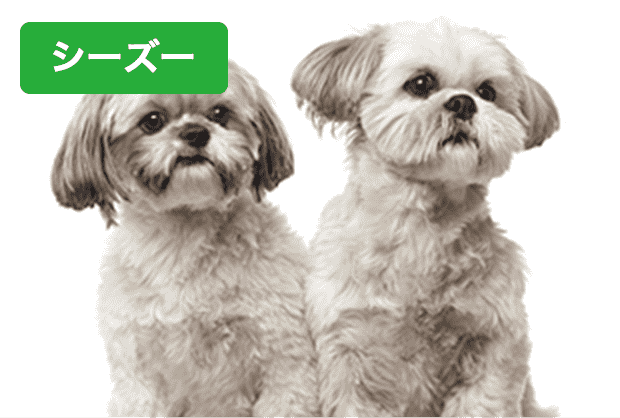
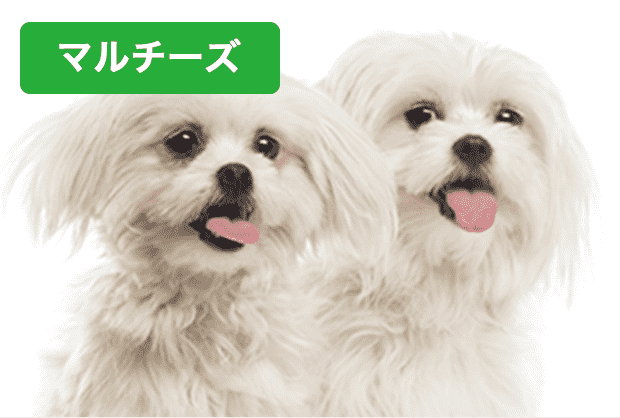
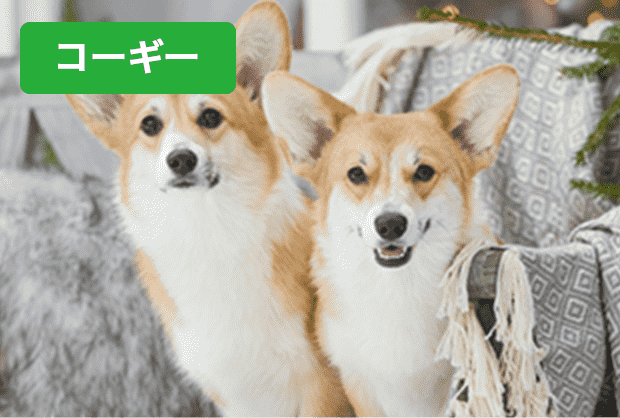



 最新記事一覧
最新記事一覧



















