
「犬の散歩ってどれくらい時間をかければ良いんだろう?」とお悩みの方も多いかと思います。そこで今回こちらでは、犬のサイズや年齢に合わせた正しい散歩時間・回数・頻度などの目安を、分かりやすくまとめてみました。
また、散歩中に必要な持ち物・散歩デビューのタイミング・散歩中のマナーなど、気になる点についてもすべてお伝えしていきます。

目次
【サイズや犬種・年齢別】散歩の時間や回数の目安まとめ!

犬が必要とする散歩量は、体の大きさや犬種・年齢によって異なります。また、その犬の性質や特徴、健康状態に合わせて微調節してあげることも大切です。
まず始めに、一般的な目安とされている散歩量について【サイズや犬種・年齢】のカテゴリーに分けてまとめてみたので、順番にご覧ください。
【サイズや犬種別】散歩の理想的な時間はこれ!
| サイズ | 1回の時間 | 1日の 散歩回数 |
主な犬種 |
|---|---|---|---|
 小型犬 |
20~30分 | 1~2回 |
|
 中型犬 |
30~60分 | 2回 |
|
 大型犬 |
60分前後 | 2回 |
|
かなり大まかなので目安が付きにくいかもしれませんが、「小型犬よりも中・大型犬の方が長い時間歩く必要がある」という事は、ざっくりと分かって頂けるかと思います。
ただ気を付けておきたいのは、小型犬でも犬種によっては中・大型犬並みに運動量が必要になる場合もあるという事です。
具体的な例としてトイプードルを挙げてみます。トイプードルは比較的小柄なコも多く、非常に人気です!ただ、「思ったよりも運動量が多いな」と感じている飼い主さんも少なくありません。
もちろん、すべてのトイプードルに当てはまるわけではありませんが、犬種的に運動量が多い傾向にあると言われているのも事実です。
【子犬・老犬】年齢に合わせて散歩の時間を調節しよう。
| ライフステージ | 散歩時間のポイント |
|---|---|
 子犬 (小型:10ヶ月まで) (中型:12ヶ月まで) (大型:15ヶ月まで) |
|
 老犬 (7歳~) |
|
成犬に関しては、先ほどお伝えしたサイズ別の散歩時間をそのまま参考にして頂ければと思います。子犬・老犬に関しては、目安よりも少なめの時間で調節してあげるのが良いでしょう。
子犬の場合、5分、10分、15分……といった形で、散歩の時間を成犬の目安までゆっくりと持っていく事をおすすめします。慣れるまで無理に歩かせるのはNGです!
また老犬の場合は、自然と活動量が落ちてくる時期が訪れます。愛犬の様子を伺いながら、散歩の時間やコース等を考え直してみるのが良いかもしれません。
例えば今まで30分散歩していた子であれば、20分に減らして様子を見てみるのも良いでしょう。とにかく無理をさせないということが一番大切になってきます。
ちなみに、翌日に疲れが残るような運動はおすすめできませんが、日々の少しずつのお散歩は続けられる限り続けた方が脳にも適度な刺激になりおすすめです。
犬の散歩は毎日行くのが理想!
- 運動不足解消
- ストレス発散
- 骨や筋肉の健康サポート
- 犬の社会性をはぐくむ
- 飼い主とのコミュニケーション
- 本能である探索活動の欲を満たす
基本的に、毎日犬を散歩に連れて行くことをおすすめします。というのも、犬の散歩には上記で挙げたような様々なメリットがあるからです。
犬の肉体的・精神的な健康をサポートするのはもちろん、飼い主との信頼関係を構築できたり、犬の社会性を育てることができるのは大きなメリットだと言えます。
かつては「小型犬だと散歩は必要ない」と言われていた時代もありました。しかし、ストレス解消などのメリットが大きいため、今では「どんな犬でも散歩は必要」だという考えが主流になってきています。
【犬の散歩に必要な持ち物】バッグの中に入れるグッズはこれ!
続いては、犬の散歩に必要な持ち物についてです。犬に装着するグッズ・飼い主のバッグの中に入れておきたいグッズに分けて、分かりやすくお伝えしていきますね!
【犬に装着するグッズ】首輪orハーネス・リードは散歩に必須。

| グッズの画像と名前 | 特徴 |
|---|---|
 首輪 |
首に装着するタイプ。犬の動きを止める・促すといったコントロールをしやすい。 ※特に小型犬やパピーでは、ぐっと引っ張ったときに首を痛めるリスクもあるので注意が必要です。また、犬がバックすると抜けてしまうことも多いです。 |
 ハーネス |
胴体に装着するタイプ。上半身を全体で支えるため、体への負担を最小限に抑えられる。 ※稀に脇が擦れて皮膚炎になったり、形状によっては気管に負担がかかる場合もあるので、愛犬にフィットしているかよく様子を見るとよいでしょう。 |
 リード |
首輪orハーネスと飼い主さんを繋ぐグッズ。犬の行動範囲を制限する役割がある。 |
愛犬はもちろん、すれ違う犬や人の安全を守るためにも、リードをつける事はとても大切です。
散歩時はリードは短め、河原など安全性が確保された場所である程度自由に走らせるのならロングリードに付け替えるのが良いかと思います。
長さを調節できる巻き取り式のリードは、トレーニングや安全性の観点からは推奨されていません。
そして、リードを繋げる先にあるのは首輪orハーネス。犬によって合う・合わないがあるので、どちらか好む方を着けてあげるのが良いでしょう。
小さい頃から慣らしていないと、ハーネスに足を通すのを嫌がる子も意外と多いです。子犬の頃から慣らすか、足を触らなくても装着できる形のハーネスを利用するなどするとよいでしょう。
【散歩バッグの中身】トイレの後処理・水分補給グッズ。

| グッズの画像と名前 | 特徴 |
|---|---|
 ティッシュやトイレペーパー |
犬のうんちを処理する時に使う。 |
 エチケット袋 |
犬のうんちを入れておく袋。 |
 うんちをキャッチするアイテム |
犬がうんちした時に拾う用。(写真は、トングにエチケット袋とペーパーを設置してクリップで留めたもの。) |
 水 |
|
 飲み水用の器 |
水を入れて愛犬の水分補給を行う。ボトルと器が一体型になっているものもある。 |
散歩バッグは、両手が空くタイプのものがおすすめです。片手でリードを掴み、片手で必要なものをすぐ取り出せるようにしておくのが良いでしょう。
バッグの中に入れておきたいメインのアイテムは、トイレの後処理に使用するもの。
おしっこをした後はそのままにせず、ちゃんと水で洗い流しましょう。またうんちをした場合は、ティッシュ等にくるんだ状態でエチケット袋に入れて、持ち帰ることが最低限のマナーです。
とは言え、将来的に犬が外で排泄することが社会的にNGになる可能性もあります。お家の中で、ペットシーツで排泄できるようにトレーニングしておくと、散歩前に排泄を済ませてから散歩に行くことも可能になるので、ぜひ検討してみて下さい。

↑ちなみに、こちらは本記事のライターである私がいつも使用している「うんちをキャッチするアイテム(自作)」です。愛犬がうんちをするタイミングで、サッとお尻の下に持って行くだけで簡単にキャッチできます◎
いつから始める?子犬の散歩デビューまでの流れ!
こちらでは、子犬の散歩デビューまでの流れについて、分かりやすくお伝えしていきます。
子犬の散歩デビューは社会化期の間がおすすめ!

ペットショップ等では「子犬の散歩デビューはワクチン接種が終わってから」と推奨している所も少なくありません。
しかし、ワクチネーションプログラムが終わるまで待っていると、社会化期が終わってしまいます。散歩に慣れることができず、その後一生散歩が苦手になってしまう子も多いです。
「全て終わるのを待たずになるべく早く散歩をスタートさせるべき」というのが、獣医行動学の専門医の先生の考え方になります。
パピーで散歩するときは、下記の注意点をお伝えしています。
- はじめは抱っこで
- 抱っこの時も必ず首輪かハーネス、リードをつける(お出かけする時の習慣にするため、万が一逃亡したときに捕まえやすくするため)
- 慣れてきたら、安全が確認できる場所で歩く練習をする(他の犬との接触は避ける、落下物の誤食に注意する)
狂犬病まで待っていたら、生後5ヶ月近くなってしまいます。この頃の子犬はもう人間でいうと9~10歳くらいだと言われています。
仮にその年まで外に出たことがない子供がいたとしたら、その後の生活は大変になることは想像がつきますよね。
ペットショップやブリーダーは感染症のリスクを避けるため、散歩の時期を遅らせるようアドバイスすることもありますが、子犬の散歩デビュー時期については考える必要があると言えます。
散歩デビューさせる前に「慣らし」を行う。

何も準備をしないままいきなり散歩デビューをさせてしまうと、散歩は恐いものだと感じてしまうケースもあります。そこでおすすめなのが「慣らし」を行う事です!
「慣らし」自体は、おうちに来て、体調が落ち着いた1~2週間後からすぐにはじめてほしいです。ペットカートや抱っこ紐を活用して、近場を歩いてみましょう。そうすると外のニオイや音にだんだんと慣れてきます。
ちなみに他の犬に慣れるために、パピークラスなどの参加も検討するのもおすすめです。
お家で首輪やハーネス+リードに慣れておく。

本格的な散歩が始まる前に、お家の中で首輪やハーネス+リードを着けて、歩く練習をしておきましょう。散歩デビューと同時にいきなり装着すると、固まってしまったり、リードをひたすら噛んだり、首輪を気にしてずっと掻いてしまう子も多いです。
装着の練習をして、うまく出来たらしっかりと愛犬を褒めてあげましょう。子犬のうちは、おやつがなくても飼い主が褒めるだけで十分報酬になります。
まずはおやつなしで、アイコンタクトをして褒めることから始めるとよいでしょう。
犬の散歩中に守るべき5つのマナー!
- リードは絶対に装着する
- 他の犬や人とすれ違う時は細心の注意を払う
- 他の犬と交流させる時は、飼い主さんに了承を得る
- おしっこをした後は水をかける
- うんちを路上に残さない
リードを着ける事は最低限のマナーです。愛犬はもちろん他の犬や人を傷つけないためにも、リードで行動範囲をある程度制限しておきましょう。
また飼い主自身が愛犬と他の犬や人の間に入る事で、トラブルを回避できることもあります。すぐ対応できるように準備をしておくのが大事です。
もう一つマナーとして大切なポイントは糞尿の処理。昔とは違って今は、おしっこをした後に水をかけて掃除をするのがマナーとして浸透してきています。
また、うんちを路上に残さないのも飼い主の義務だと言えるでしょう。もしゆるめのうんちが出た場合は、路上にこびりついている部分を水で流して綺麗にしておく事が大切です。
上手な犬の散歩にはしつけが大事。重要な2つのポイント!
- リーダーウォークを徹底する
- 基本的なコマンドを覚えさせておく
続けて、上手に犬の散歩を行うために重要なポイントを2つお伝えしていきます。
飼い主との歩調を合わせる「リーダーウォーク」

飼い主側の主導で愛犬を歩かせるのがリーダーウォークです。飼い主よりも犬が先に歩いて引っぱられるのではなく、付かず離れずのちょうど良い距離感を保ちながら歩調を合わせて歩くのが基本になります。
- 飛び出し事故を防ぐ
- 拾い食いを防止できる
- 他の犬や人への攻撃を避けられる
- 首輪の締め付けが発生しない
- 飼い主側の負担が減る
リーダーウォークを行うことで、上記のようなメリットを得られます。好奇心旺盛なコだと、飼い主さんよりも先に動いてグング引っ張ってくる……!なんて事は、あるあるですよね。
その時に大切なのは、引っ張り返すのではなく「止まる」というアクション。ちゃんと飼い主さん側に戻ってきたら、おやつ等を与えてしっかりと褒めてあげましょう。
こちらを繰り返すことで、徐々にリーダーウォークが身に付いていきます。
「待て」などのコマンドを覚えさせておく。

基本的なコマンドを覚えさせておくと、散歩の時に役立つことは間違いありません。例えば、愛犬が興奮しすぎて引っ張られるシーンで「待て」を使用すると、落ち着いてくれたりします。
他にも「来い」や「伏せ」などを使い分けることができると、さらに良いでしょう。落ち着いた状態をキープしつつ散歩をすることで、思いがけない事故を防ぐこともできます。
難しい場合は、ドッグトレーナーによるしつけ教室やマナーレッスンの受講を検討してもよいでしょう。
訓練所などに犬を預けるパターンもありますが、飼い主自身も勉強が必要なので、できれば飼い主と犬が一緒にレッスンを受けた方がよいです。
愛犬の満足度UP!散歩のコツ3選!
- 散歩コースを変える
- 遊びを取り入れる
- 歩くスピードを変えてみる
こちらでは、愛犬により散歩を楽しんでもらうためのコツを3つのポイントにまとめてみたので、順番にご覧ください!
散歩コースを変えてマンネリ化を防ぐ。

同じ散歩コースを毎日歩いていると刺激がなくなるので、時には思い切って散歩コースを変えてみましょう。コースを変えると喜んでくれるコはとても多いです。
もしコースの選択肢があまりないのであれば、いつものコースを逆回りしてみるのも良いでしょう。
ただし臆病な犬や老犬の場合、いつもと違うことに不安を感じて歩かなくなってしまうケースもあります。そんな時は無理にコースを変えなくても大丈夫です。いつものコースで安心させてあげるのが良いでしょう◎
おもちゃ等で遊びを取り入れる。

散歩コースの途中に公園や広場があるなら、そこでボールなどのおもちゃを使った遊びを取り入れてみましょう。
犬にとっていい運動になるだけでなく、飼い主さんと遊んでいるという充実感が得られるので、いつも以上に満足度がUPします。
シニア犬で食欲がなかったりする場合、散歩先の公園でフードをあげるとピクニック気分で楽しくなって食べることもあります。
歩くスピードを変えてみる。

いつも同じスピードで散歩しているなら、時には速度にメリハリをつけて愛犬を楽しませてみるのもおすすめです。早歩き、小走り、本気走りなどなんでもOKです。
とくに走る行為は、ただ歩くよりもいい運動になります。忙しくて散歩に多くの時間を割り当てられない人は、短い時間の中で走る散歩をしてみるのもいいでしょう。
【雨の日や夏冬など】気温や天気に合わせた犬の散歩方法!
雨の日や真夏・真冬の散歩はどうすれば良いのか、疑問に思っている方も多いかと思います。こちらでは、天気や気温に合わせた犬の散歩方法についてまとめてみました。
雨の日は無理に散歩しなくてOK!

雨が降っている日は無理に散歩しなくても大丈夫です。繊細な子だと、雨に濡れる・レインコートを着せられることを嫌がる場合もあります。
そういう事でストレスが溜まるくらいなら、雨の日はお家で運動させてあげる方が精神的にも良いでしょう。
ただし、外でしか排泄を行わない犬の場合、雨の日でも散歩は必要になってきます。雨が弱まっているタイミングで出かけたり、屋根が多く濡れにくいコースを選んだりするのがおすすめです。
散歩に行けず運動できない日が続いた場合は、知育玩具などを使って頭を働かせられる遊びを積極的に行ってあげると良いでしょう。頭を使うことで心地よく疲労し、睡眠の質が上がることが犬でもわかっています。
夏の散歩は熱中症対策が超大事!

- 朝方や日が沈んだ後など、涼しい時間帯を選ぶ
- 日陰が多いコースを散歩する
- 水分補給の準備を徹底しておく
- 氷のう・タオルなど、保冷グッズを用意しておく
- あまりにも暑い日は、外での散歩を止めておく
夏は気温が25℃を超えてきたあたりから熱中症のリスクが上がります。犬は地面との距離が近いので、人よりも暑さを感じやすい=熱中症になりやすいんです。
熱中症は、最悪死に至るケースもある恐ろしい病気。なので、熱中症を起こさないよう対策しておくのが一番大切になってきます。
また、万が一熱中症を起こしてしまった場合は、スピーディな応急処置+病院に連れて行くのが正しい行動です。
冬の散歩は低体温症NG!

- 日中の暖かい時間帯を選ぶ
- 日当たりの良い散歩コースを選ぶ
- 散歩に出かける前、軽い運動で体を温めておく
- 防寒アイテムを着用させる
- あまりにも寒い日は、外での散歩を止めておく
何らかの原因で、体温が37.5℃以下になってしまうのが「低体温症」。冬の散歩で体が冷たくなりすぎると、低体温症を引き起こしてしまう場合があるんです。
低体温症になってしまうと、元気がなくなる・血圧や心拍数が低下する等の症状が出てきます。またあまりにも体温が低くなりすぎると、死に至るケースもあるので注意が必要です。
もし低体温症を起こしてしまった場合、自己流で体を温めると低温やけどに繋がる可能性も。基本的にはすぐ病院に連れて行ってあげましょう。
犬の散歩に関するよくあるQ&A
最後に、犬の散歩に関するよくある質問とその答えをいくつかお伝えしていきますね。
わがままな愛犬が散歩中歩かない。どうすれば良い?
- できるだけ反応をせずにじっくりと待つ
- 軽くリードを引っ張ってみる
- アイコンタクトで「行くよ」と伝える
わがままで散歩中に立ち止まってしまう場合、この3つの方法を試してみる事をおすすめします。
こんな時にやってしまいがちなのは、抱っこをする・おやつで釣るといった行動です。甘やかしが重なることで「止まると抱っこしてくれるんだ」「おやつが欲しいから止まってみよう」といった学習をしてしまいます。
犬が散歩を嫌がる理由は何?
- 散歩に恐怖を感じている
- 首輪が合っていなくて苦しい
- ケガや関節のトラブルが生じている
- 病気にかかっていて元気喪失している
- 十分に社会化できていない
- 老化により体力が衰えてきている
- 外の気温が暑すぎる・寒すぎる
犬が散歩を嫌がる理由は多岐にわたります。上記では考えられる主な理由を7つにまとめてみました。
愛犬の様子をしっかりと観察しながら、当てはまるパターンがあるのかどうかをチェックしてみましょう。必要な場合は、病院で健康状態を診てもらうことも検討してみて下さい。
夜の散歩中は犬の首輪にライトを着けた方が良い?
ライトが内蔵されているタイプの軽い首輪はたくさん販売されているので、愛犬に合うものを選んでみて下さい。また、飼い主さんの腕に装着できるタイプのライトを併用して使うのもおすすめです。
食後1時間で犬を散歩に連れて行くのは正しい?
犬によって消化のスピードが違ってくるので、この点は個体差が出てくるところでしょう。念のため、食後は2~3時間あけて散歩に行くのが安全だと思います。
大型犬の場合は、食後すぐに散歩をさせる事で「胃捻転(いねんてん)」という病気のリスクを上げると言われているので、特に注意が必要です。
小型犬を飼っているんだけど、週末だけ散歩をするというスタイルはダメ?
外の空気に触れるだけでもリフレッシュに繋がるので、できる限り毎日時間を作ってあげましょう。
犬の散歩に便利な給水ボトルが欲しい!おすすめはある?

個人的におすすめなのは、このように押すと水が出てくるタイプの給水ボトルです!愛犬が水を飲みたそうにしている時、サッと用意してあげられます。
犬の散歩のバイトをしてみたい。どうやって探したら良いの?
Indeedや求人ボックスなどの求人がいくつか出てくるので、そちらから問い合わせてみるのが良いでしょう。
他の方の愛犬を預かるということは責任重大ですので、きちんと勉強をした上で行うことを強くおすすめします。
犬の散歩は行かないとどうなるの?
ストレスが溜まってしまう可能性が高いです。ストレスは様々な病気を引き起こすリスクを上げてしまうので、愛犬の健康のためにも散歩に連れて行ってあげましょう。
正しい散歩で愛犬の健康をサポートしよう!
- 犬が必要とする散歩量は、体の大きさや犬種、年齢によって異なる。
- 毎日散歩に連れて行くのが理想。肉体的・精神的な健康をサポートできる。
- 子犬はワクチン接種が完了していなくても、危険がないように注意しながらなるべく早く散歩の慣らしを始める。
- 散歩中のマナーをしっかり守ることは飼い主の義務。
- 上手に散歩をするためには、しつけが必要になってくる。
- 犬の散歩の満足度を上げるために工夫をするのが大事。
- 雨の日は無理に散歩をしなくてもOK。
- 真夏は熱中症、真冬は低体温症に気を付ける。
犬に必要な散歩量は、体の大きさや犬種、年齢によって変わってきます。またその子の性質や特徴、健康状態によっても左右されるという事を覚えておきましょう。
散歩はストレス解消・リフレッシュに繋がるので、毎日連れて行ってあげるのが理想です。愛犬の健康維持に役立つことは間違いありません。
今回は散歩に関する情報をたくさんお伝えさせて頂きました。あなたの愛犬の快適な散歩ライフをサポートするためにも、良いなと思ったポイントを実践して頂ければ嬉しいです!

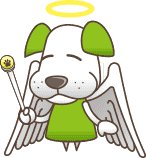



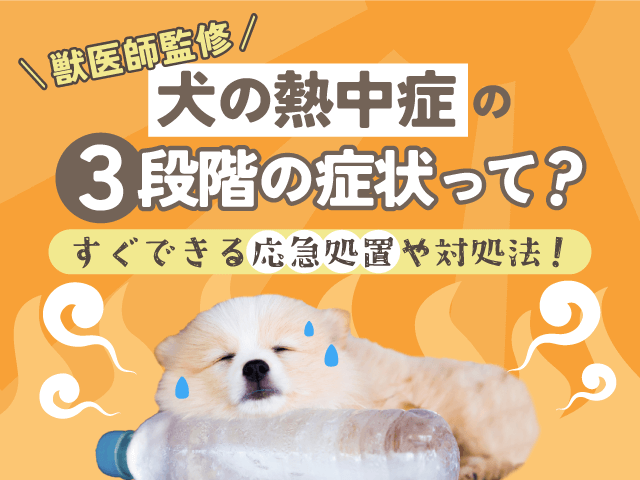
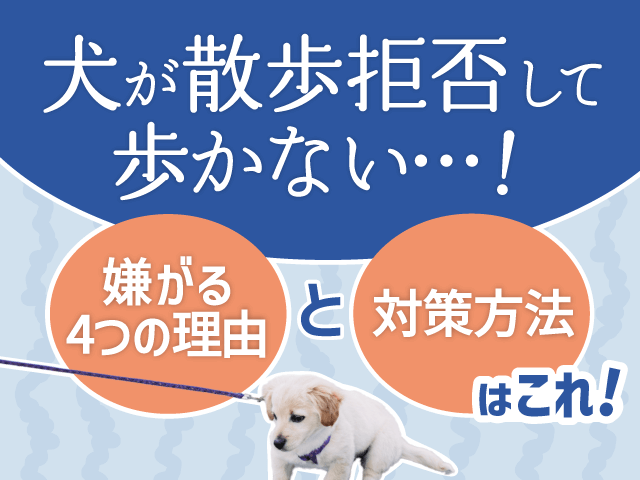
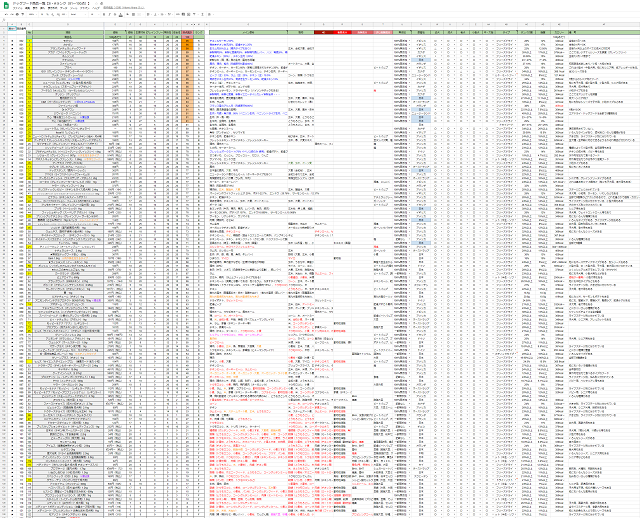








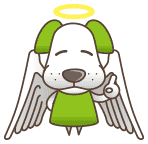

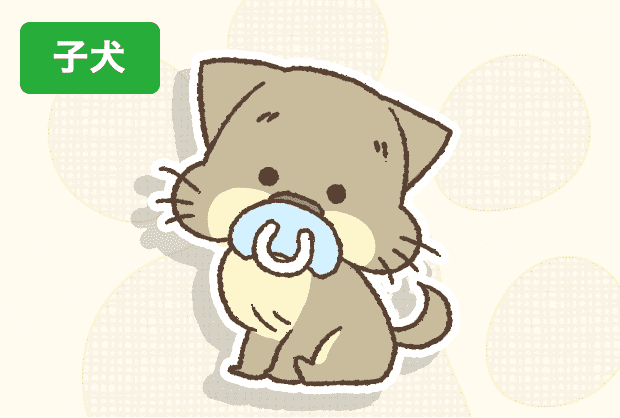
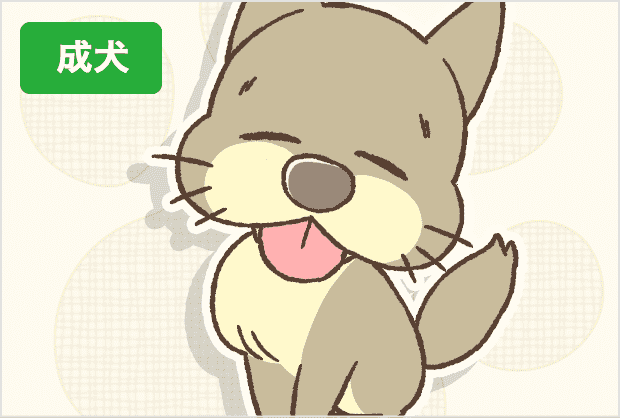
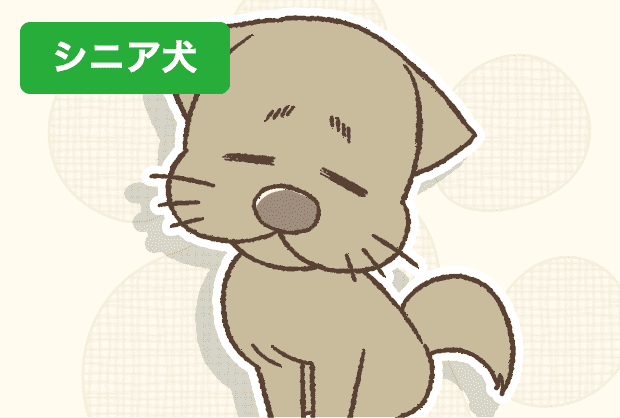


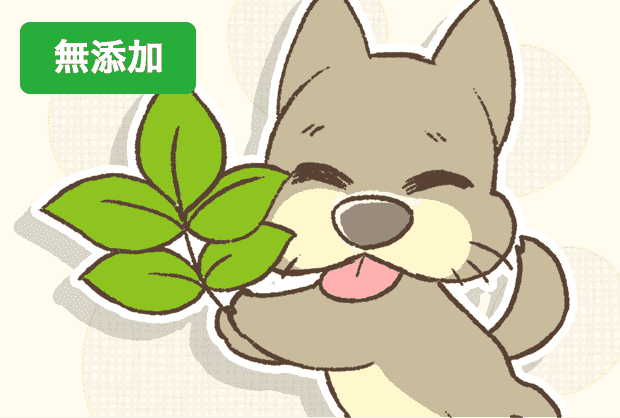


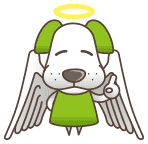







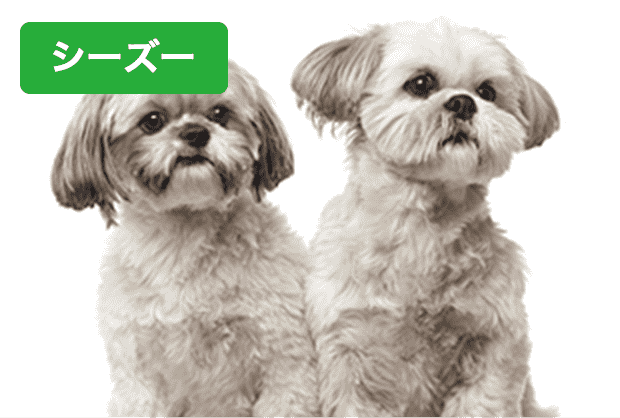
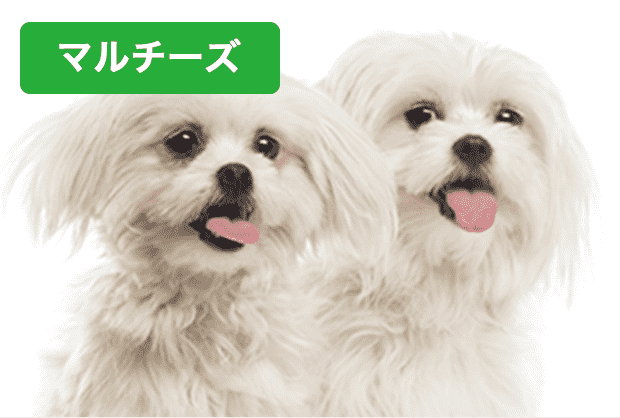
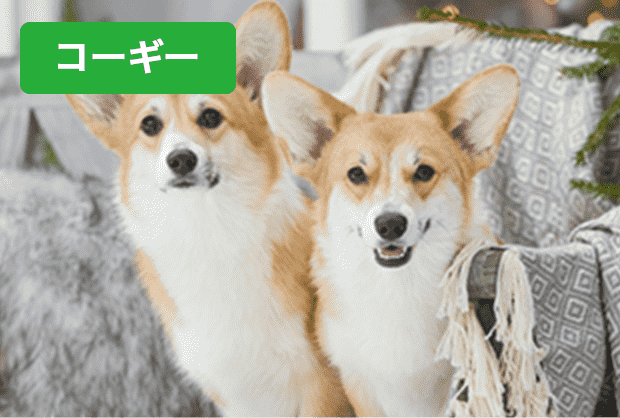



 最新記事一覧
最新記事一覧



















