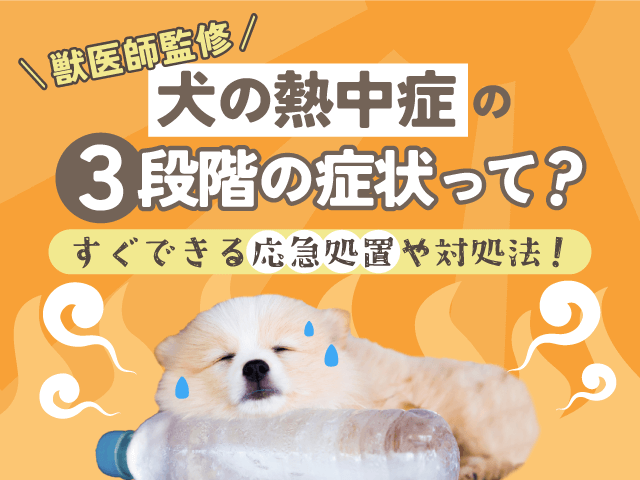
犬は「ハァハァ」と呼吸をする事でしか体温調節ができないので、人間よりも熱中症を起こしやすいと言われています。
元々、犬の基礎体温はおよそ38から39度と、人間よりもずいぶんと高めですが、そこからわずか1~2度上昇して40度を超えると熱中症を起こす可能性が出てきます。
最悪の場合、死に至るケースさえある熱中症。いち早く愛犬の異変に気付くことが大切です!こちらでは、犬の熱中症の症状を【軽度】【中度】【重度】の3段階に分けてお伝えしていきます。
また起こってしまったときの応急処置や予防法についても、獣医師の先生監修のもと分かりやすくまとめてみました。

目次
【軽度・中度・重度】犬の熱中症の症状を3段階で解説!
まずは犬の熱中症の症状を、3段階に分けてお伝えしていきます。
【軽度】激しい呼吸は初期症状のサイン

- 激しいパンティングが始まる
- 体に触れると熱い
- 落ち着きがなくなる
- よだれを垂らし続ける
犬が舌を出してハァハァと呼吸をする現象は「パンティング」と呼ばれ、これは体温をコントロールするための自然現象として知られています。
熱中症の初期には、このパンティングが早くなるといった症状が見られることが多いです。呼吸も粗くなり、落ち着きがなくなります。
犬の体温が上がっている状態なので、触れると熱を持っているような感覚が分かるかもしれません。熱中症は早期発見・対応が大事なので、こういったサインを見逃さないようにしましょう。
【中度】フラフラして立てないのは中期症状

- フラフラして上手く立っていられない
- 目や口の中が充血する
- 意識がもうろうとしている
- ボーっとして動かない
さらに進むと、呼吸がより激しくなり、ガラガラと水の音がし始めたり、フラフラとして立てない等の症状が見られます。こういった明らかな異常が見られる場合は、中度の段階である可能性が高いです。
目や口の中などの粘膜を確認すると、充血していることも少なくありません。
この段階になると、あっという間に重症化してしまうので、できる限り病院へ搬送すべき状態と言えます。
中等度からは、単に体表を冷やすだけでは表面だけが冷やされて内に熱がこもってしまい、後々重大な後遺症に繋がる事もあるので、速やかに点滴をしてもらいましょう。
【重度】嘔吐・下痢・舌の色の変色は重度の熱中症のサイン

- 嘔吐反応がでる
- 下痢が始まる
- 痙攣している
- 歯茎が白くなる
- 舌が青紫に変色する
- 嘔吐物や排泄物に血が混じる
熱中症が重症化すると、嘔吐・下痢・痙攣などの症状が出てくるケースも多いです。すぐに応急処置を行い、直ちに病院に連れて行かなければならない危険なレベルになります。
歯茎が白くなる・舌が青紫に変色する症状は「チアノーゼ」と呼ばれ、酸欠状態になっているサイン。
特に免疫力の弱い子犬や老犬の場合は、初期症状からわずか数分でここまで重症化することもあります。
愛犬の熱中症!応急処置から回復期間の過ごし方まとめ!
- 日陰に移動する
- できれば土や芝生があるところ
- 体を冷やす
- 病院へ移動
愛犬が熱中症を起こした場合、すぐに応急処置を行いましょう。こちらでは飼い主さんがすべき行動を、3ステップに分けて分かりやすくお伝えしていきますね。
「日陰に移動する」風通しの良い場所へ。

まずは日陰などの涼しい場所に移動するのが鉄則です。外で散歩中だった場合は、アスファルトを避けて風通しの良い場所に移動しましょう。
犬の熱中症の最大の原因は日光よりも路面の輻射熱です。なので、日陰であっても、または夜中であっても安心はできません。できるだけ土や草のあるところへ移動しましょう。
家の中で熱中症の症状が出ている場合は、エアコンがしっかりと効いている場所に移動します。冷水を軽く絞ったタオルで全身を拭く事も有効です。
どこに居たとしても、とにかく脱水症状を避けることが重要です。飲み水を口元まで持って行ってあげて、水分補給をサポートしてあげましょう。
「体を冷やす」冷やす場所は太い血管を狙う。

続けて体を冷やす作業を行います。首の下・脇の下・鼠径部は太い血管が通っているので、その辺りを狙って冷やすと効率が良いです。
冷やすためのグッズとしては、氷のうや水で濡らしたタオルなどがおすすめ。設置できたら、うちわやタオルなどで優しく風を送ってあげましょう。
保冷剤などを直接体に置いてしまうと、低温やけどを引き起こすかもしれないので注意が必要です。止めておくorタオルでくるんで温度が低くなりすぎないように気を付けます。
また、体を必要以上に冷やしすぎると「低体温症」を引き起こす可能性もあるので、冷やしすぎはNGです。ある程度冷えた段階で、冷やすアイテムを取り除いてあげましょう。
「病院へ移動」回復した後も油断はNG!

適切な応急処置をスピーディに行えると、回復も早くなります。ただ見た目は回復したように見えても、体の中で何が起こっているのかは分かりません。
大丈夫だと思っていたのに急変して容態が悪化する事もありますし、後遺症として何かしらの病気が残ることもあります。
なので応急処置を行ったあとは、すぐ病院に連れて行きましょう。本当に大丈夫なのかどうかを、獣医師の先生にしっかりと診てもらいます。
【死亡・後遺症が残る】犬の熱中症で起こり得る最悪のケース
犬の熱中症を甘く見てはいけません。死に至るケース・後遺症が残るケースがあるからというのが理由です。こちらでは、最悪のケースについてお話していきます。
急変して死に至るケースもある。

犬が熱中症になってしまった場合、適切な処置を早急に行わないと死亡するという最悪のケースも起こり得ます。
夏の季節になると「車の中にほんの少し置いていただけなのに……」といった、痛ましいニュースを目にする事も少なくありません。
具体的な体温で言うと40℃を超えるとかなり危険、42℃を超えると死の危険が出てきます。危険な病気である事を自覚して、夏の季節を過ごす必要があるでしょう。
熱中症の後遺症が残る場合も……。

命を落とさなかったとしても、内蔵や脳の機能障害などの後遺症が残るケースもあります。長期での治療が必要になってくることも多く、愛犬はもちろん飼い主さん側のケアも大変です。
応急処置を行った後に回復したように見えても、数日後に体の不調が出てくることもあります。
愛犬にはずっと健康で長生きしてほしい!と願うのなら、自己判断で大丈夫だと決めつけずに念のため病院に連れて行ってあげましょう。
【室内・散歩・車】犬の熱中症の予防対策まとめ!
そもそも熱中症が起きないように、飼い主さんができる対策法は色々とあります。こちらでは、【室内・散歩・車】といったシチュエーション別で、準備しておけることについてまとめてみました。
家の室内温度は25℃前後・湿度は50%前後に保つ。

犬が快適に過ごせる室内温度は、だいたい25℃前後と言われています。また湿度は40~60%の範囲が理想的です。50%前後でキープしておくのが一番無難だと思います。
常にこれくらいの温度・湿度を保てるようなエアコンの設定をしておきましょう。
ただし、エアコンの風が直接犬に当たるのは良くありません。部屋全体にまんべんなく空気を循環させることが大切です。
サーキュレーターや扇風機をエアコンと併用して、室内の空気を撹拌すると、エアコンの設定温度を1~2度上げる事ができます。
散歩にいく時は熱中症対策グッズを持参する。

- 水
- タオル
- 保冷グッズ
- うちわや扇子
真夏の散歩時には、熱中症が起こってしまった時のために対応できるグッズを持参しておきましょう。上記のようなアイテムがあれば、素早く愛犬の体を冷やせます。
また、散歩の時間を涼しい時間にズラしてあげるのもおすすめです。どうしても難しい場合は、日陰の多い散歩コースを選ぶ・短時間で切り上げるのも良いでしょう。
あまりにも暑い日なら、無理に散歩に連れて行かなくても大丈夫です。そういった日は、お家の中で思いっきり遊ばせてあげる事をおすすめします。
夏の車内は要注意!愛犬から目を離さない。

車の中は温度が上がりやすく、熱中症になりやすいので特に注意が必要です。エアコンで室内温度を適温に保ちつつ、愛犬に異変が起きていないかこまめにチェックします。
ひんやりマットを敷いてあげたり、念のために保冷グッズを用意しておくのがベストです。また、いつでも水分補給ができるような環境を整えておきましょう。
ちなみに、例え短い時間でも閉め切った車内に愛犬を残すのは絶対にNG!JAF(日本自動車連盟)が行った実験によると、「暑い日の車内はものの5分で熱中症の警戒レベルを超える」という結果が出ています。(※1)それくらい危険であることを覚えておきましょう。
熱中症になりやすい5つの犬の特徴!
- 短頭種
- 寒冷地出身
- 肥満体型
- 子犬や老犬
- 持病のある犬
こちらでは、熱中症になりやすい犬の特徴をお伝えします。愛犬に当てはまる場合は、さらに気を付ける必要があるのでチェックしてみて下さい。
鼻ぺちゃ犬と呼ばれる「短頭種」
- パグ
- シーズー
- フレンチブルドッグ
- ボストンテリア
- ペキニーズ 等
鼻ペチャ犬と呼ばれる「短頭種」は、そうでない犬と比べて呼吸の効率が悪いです。パンティングによる体温調節が苦手なので、熱中症になりやすいと言われています。
暑さが苦手な「寒冷地出身の犬」
- シベリアンハスキー
- ゴールデンレトリーバー
- サモエド
- 秋田犬 等
「寒冷地出身の犬」は、寒さに対応できるよう被毛がダブルコートになっていて、暑さを感じやすいです。熱の排出効率が悪いため、熱中症になりやすいと言われています。
熱がこもりやすい「肥満体型の犬」
皮下脂肪によって熱がこもりやすい「肥満体型の犬」。首まわりの脂肪が気道を圧迫して、呼吸がしにくい子もいます。
こういった要素が重なって、熱中症の症状に拍車をかけてしまう可能性があるので注意が必要です。
体温調節が苦手な「子犬や老犬」
「子犬や老犬」は、体温調節が苦手な子も多いです。免疫機能が十分ではない場合もあり、熱中症になりやすい要素が揃っていると言えます。
体力がない「持病のある犬」
「持病のある犬」は、体力がないというケースも少なくありません。全般的に熱中症になりやすいと言われていますが、特にその中でも呼吸器系の疾患や心臓病を患っている場合は要注意です。
どちらも心肺機能が衰えていますのでガス交換がうまくできず、通常よりももっと低い気温でも熱中症を引き起こす事があります。
コンクリートやアスファルトの多い都心部や、九州地方などでは5月のゴールデンウィーク頃でもお天気や車内など条件次第では熱中症を発症する事があります。
犬の熱中症に関するよくあるQ&A
最後に、犬の熱中症に関するよくある質問とその答えをいくつかお伝えしていきます。
愛犬が熱中症っぽいけれど、水を飲まない。どうすれば良い?
ただしあまりにも長く続くようだと、脱水症状に繋がってしまう場合もあります。
飲みやすいスプーンなどに少量の水を入れてから与えてみたり、ささみのゆで汁のような香りが付いている水分を与えてみるといった方法を試してみる価値はあるでしょう。
気温が何度になってから犬の熱中症予防をするべき?
アスファルトの路面では輻射熱により夜中になっても路面が熱い事がよくありますので、散歩の前に路面を触ってみて熱を確認する事も重要です。
気温が高い日は熱中症予防グッズを持って散歩に行きましょう。また、30度を超える日は散歩を控えることも検討してみて下さい。
愛犬をお留守番させる時の熱中症対策が知りたい。
何かあった際すぐチェックできるように、ペットカメラを設置しておくのも良いと思います。
あまりにも暑い日は、よほどのことがない限り長時間お留守番をさせないようにするのも大事です。
犬の熱中症で痙攣が起きた時の対処法は?
痙攣が起きているのであれば、熱中症が重症化している段階である可能性が高いです。応急処置を行ってから、すぐ病院に連れていきましょう。
犬の熱中症。病院ではどんな処置・治療を行うの?
脱水症状やショック状態改善のために点滴を行うこともあります。また、重大な酸欠状態に陥っている場合であれば、酸素投与を行うこともあるでしょう。
犬の熱中症は予防が一番大事!起こった際は早急な対処を。
- 初期症状としてよく見られるのが「激しいパンティング」。
- 重症化すると嘔吐・下痢・チアノーゼなどの症状が現れる。
- 応急処置の3ステップは、涼しい場所に移動→体を冷やす→病院に連れて行く。
- 死に至るケース・後遺症が残るケースもある。
- 普段から熱中症予防を意識することが大切。
- 室内温度は25℃前後・湿度は50%前後に保つのがベスト。
- 真夏の車内の温度はすぐに上昇するので本当に危険。
犬の熱中症は、最悪死に至るケースもある恐ろしい病気です。熱中症になってしまった場合は、早期発見・対処が必要となってきます。
また、応急処置を行った後は基本的に病院に連れて行くのが鉄則。回復したように見えても、体の中で何が起きているのかは分からないので、獣医師の先生にしっかりと診てもらいましょう。
そもそも熱中症にならないような対策を普段から意識しておくことも大事です。室内・散歩時・車の中、それぞれの環境で対策を行い、愛犬を熱中症の危険から守りましょう。
※1(暑い日の車内で起こる危険!)安全運転ほっとニュース|東京海上日動

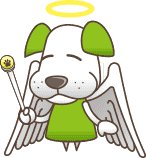

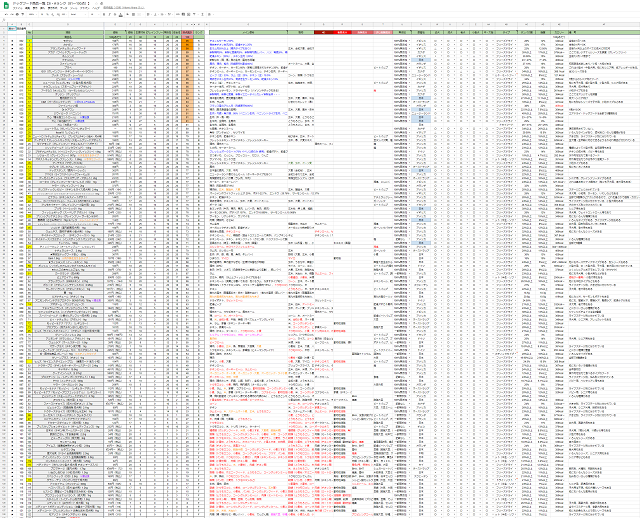


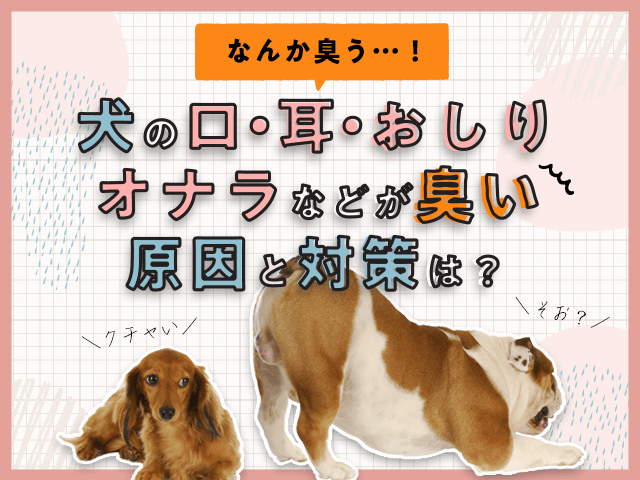

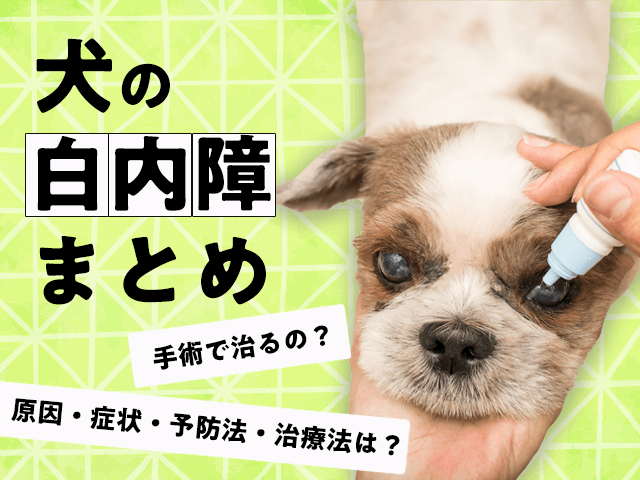



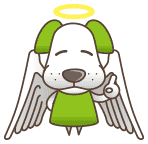

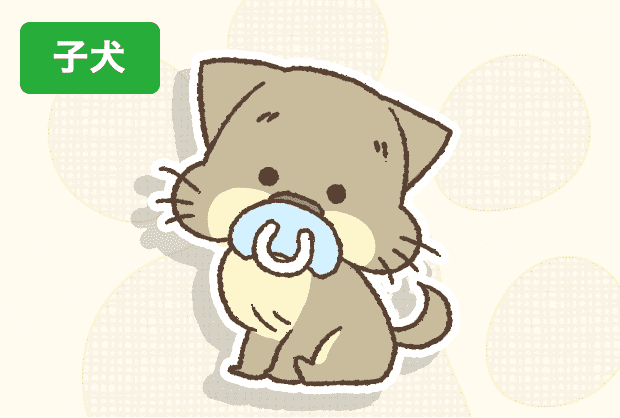
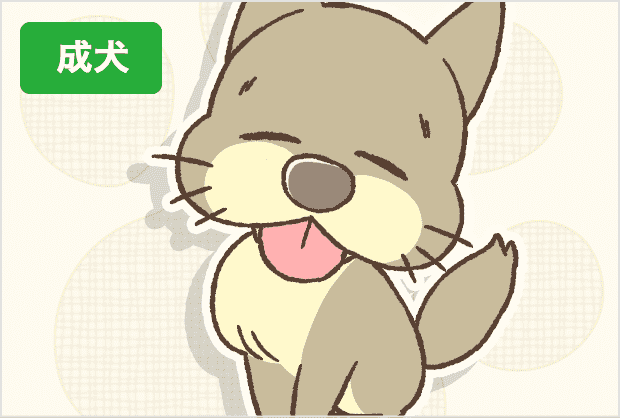
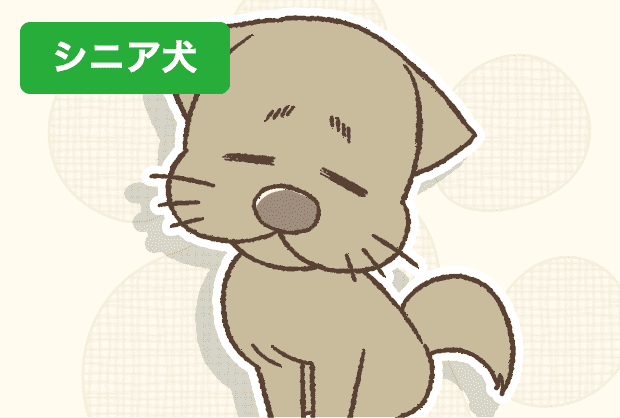


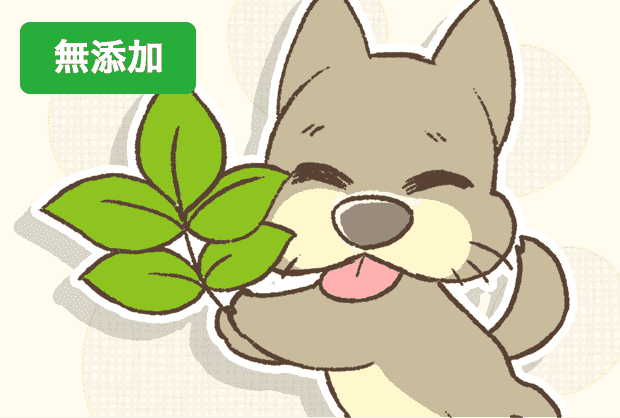


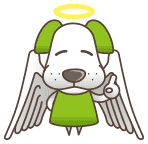







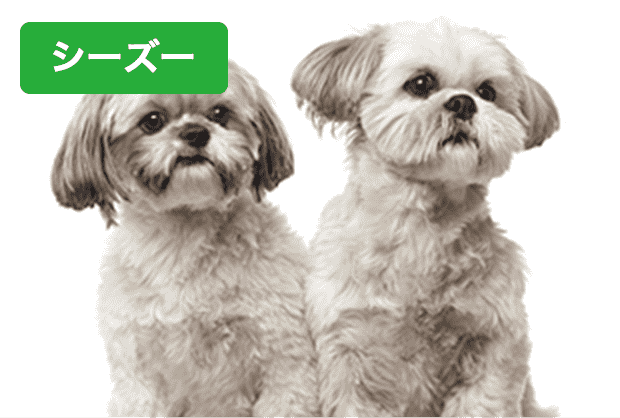
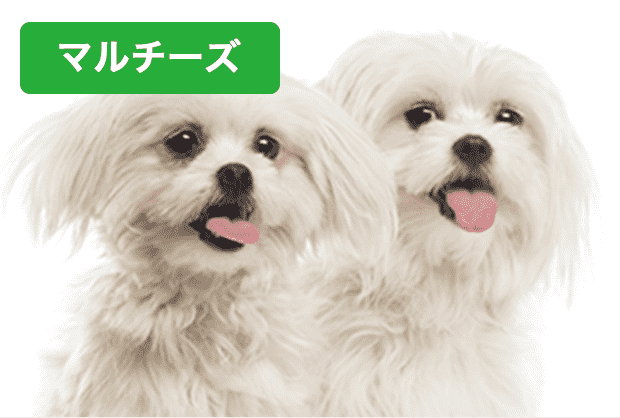
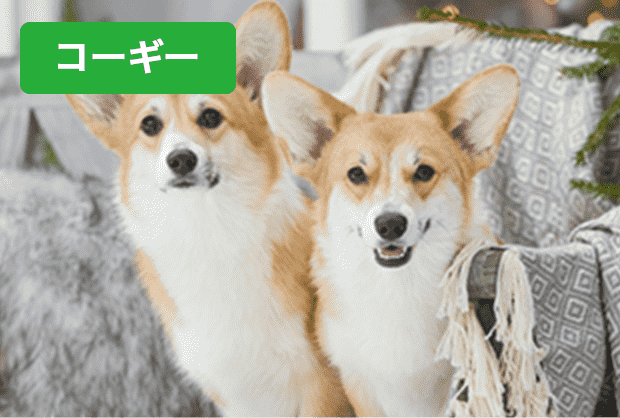



 最新記事一覧
最新記事一覧



















